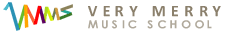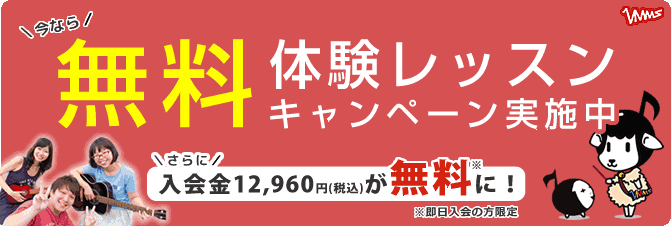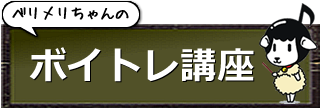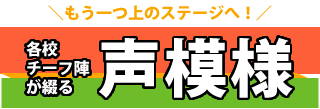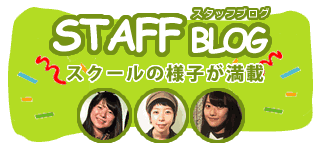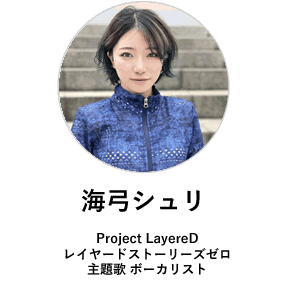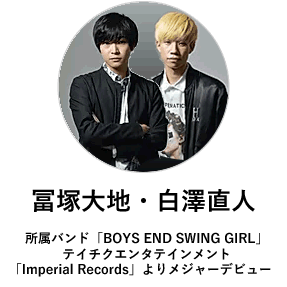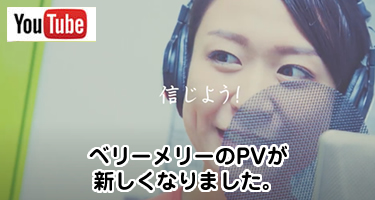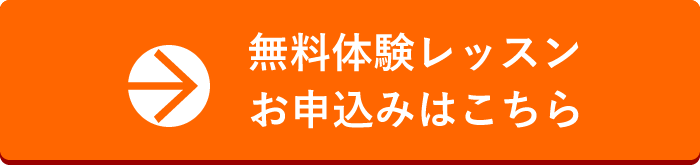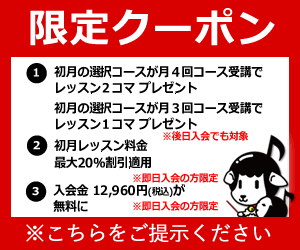3月に入り、暖かくなって来たかと思ったら寒かったり!えーっ!マジかー?みたいな気候が続いて、まいっちゃいますよね!
必ず春は来ます!ここは心機一転、歌唱力をステップアップさせたいあなたに、様々なテクニックを学ぶのにぴったりな春の曲セレクションをご紹介します。
はじめに
「歌がうまくなる」と一口に言っても、歌のうまさには実に様々な側面があります。
・音程(ピッチ)
・リズム
・アーティキュレーション(音の形・メリハリ)
・声量
・伸び
・気持ち・バイブス
・etc…
これらを一つ一つ押さえていくことで、真のうまさを追求したボーカリストになることができます。
どのように練習すればいいのでしょうか?私は、とにかく世の中に存在する様々な曲をどんどん練習し、それぞれを歌いこなせるようになっていくのが重要だと思います。そして曲を選ぶときは、曲調やボーカリストの歌い方などから、上に挙げたような項目のなかでも特にこの観点!という風に、身につけたいスキルに合った適切な曲を選ぶのが良いでしょう。
今回は、ちょうど今の桜が咲く時期にぴったりな曲を、レベル・観点ごとにご紹介します。
初級編

明日、春が来たら / 松たか子
(動画URL)https://www.youtube.com/watch?v=XzXG2rj0a1o
1997年にリリースされた、松たか子さんの曲です。曲全体ではそこまで大きく曲調が変わることなく、比較的落ち着いたリズムなので、ボーカルに慣れていない方でも発声に集中して歌うことができるでしょう。
この曲で重視したいのは【音程】です。メロディの一つ一つの音符に集中して、確実にピッチを捉えることを意識して、丁寧に歌うことを心がけましょう。
中でも気をつけたいのは、Aメロを中心に出てくる「弱起」(小節をまたがる前から始まる音)の部分です。例えば、曲冒頭の
– 走る / 君を見てた
– 白い / ボールきらきら
のように、/ の前の単語はそれぞれ弱起にあたります。/ の直後の音符に気を取られておろそかにならないように気をつけてみてください。
また、Bメロも全体的に音程を気をつけたいところです。原曲ではハモリが入ってくるため、つられないようにメロディラインを歌い上げましょう。たまに入ってくるファルセット(裏声)も聴かせ所ですので、何度も練習して安定した音程で歌えるように頑張りましょう。
桜坂 / 福山雅治
(動画URL)https://www.youtube.com/watch?v=AGYJ6jeu3p8
今でも幅広い層にカラオケで歌われる、2000年にリリースされた福山雅治さんの曲です。こちらも落ち着いたリズムのため、比較的歌いやすいと思います。
この曲で重視したいのは【声量】【雰囲気】です。原曲を聞けばお分かりの通り、この曲は声量が大きすぎては切ない雰囲気を出すことはできません。そのため、声量をコントロールしつつ、時には(軽いため息のような)空気音を混ぜたりしながら、福山さんの色っぽい歌い方も含めてカバーできると良いでしょう。
サビは少し声量を上げたほうが盛り上がりますが、そのぶんAメロ、Bメロは特に注意が必要です。歌い出しから声量が大きめだと、サビがかなり元気になってしまい、曲の雰囲気に合わなくなってきてしまうためです。
もう一つ上のレベルを目指したければ、音符単位で音量の強弱をつけてみるとより雰囲気が出るでしょう。例えば冒頭歌いだしでは、
「きみよずっとしあわせに〜」
のように、下線が付いた音を少し大きく(というより、少し力を込める程度)してみると、より福山さんらしいニュアンスに近づくと思います。原曲を注意深く聴きながらコピーしてみましょう。
中級編

冬と春 / back number
(動画URL)https://www.youtube.com/watch?v=hu6y1ol9yUg
昨年1月にリリースされたback numberの楽曲です。ボーカルの清水さん自身が初めてミュージックビデオの監督を務めたとのことで、今までより一層ストーリーが際立った作品となっていると思います。
そんなこの曲で重視したいのは【アーティキュレーション(音の形・メリハリ)】です。より具体的に言えば、この曲のストーリーの詳細をより一つでも多く伝えるように、歌詞に感情を込めて、語るように歌うのがポイントだと思います。つまり、棒読みにならずに、一つ一つの単語を聞き手に言葉として伝えるような音の形を作る必要があります。
物語性を伝えるためには、背景を印象付ける必要があるので、やはり出だしが大事です。
「私を探していたのに 途中でその子を見つけたから」
ここだけでも既に切なさが伝わる1フレーズとなっていますが、試しに一度、このフレーズだけ特に何も考えずに歌ってみてください。その次に、このフレーズの意味をしっかりと聞き手に届けるように再度歌ってみましょう。何回か繰り返し、歌声に深みが出てきたら、次のフレーズに進んでみます。
これを1曲通して続ければ、きっとこの曲の切なさがしっかり伝わる味のある歌声になっているはずです。
SAKURA / いきものがかり
(動画URL)https://www.youtube.com/watch?v=61z-cqg28R8
2006年にリリースされた、桜の曲ならこれ!ないきものがかりの1曲です。ボーカルの吉岡さんは可愛らしい歌声を持つイメージを持つ方もいるかもしれませんが、実は喉がしっかりと開いた芯のある歌声の持ち主です。
この曲で重視したいのは、ずばり【発声】【伸び】です。曲全体を通して、喉を締めて細い声が出てしまうことがないよう、常に気をつけておくようにすることがポイントです。これをマスターすれば、Aメロからサビに向けて伸びやかな安定した声を維持し、盛り上げていくことができるようになります。
Aメロ・Bメロの盛り上がる前でも、あくまで喉を開けておくことを忘れず、息の量などで音量を調節するようにしてください。そして、ここから雰囲気を変えるのはBメロの次の歌詞の部分です。
「(小田急線の窓に)今年もさくらが映る 君の声が(この胸に聞こえてくるよ)」
こうした盛り上がりのために重要なフレーズも、勢いをつける余りに喉を締めてしまいがちです。こういったポイントこそ、意識的に喉を開けるようにすると良いでしょう。
上級編
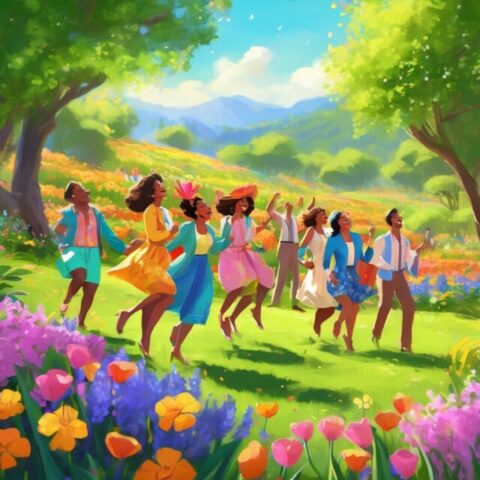
(動画URL)https://www.youtube.com/watch?v=DC6JppqHkaM
2020年にリリースされた楽曲。yamaさんがブレイクするきっかけとなった、初のオリジナル曲だそうです。何と言ってもボカロ出身の打ち込みをベースとした早いテンポのリズムが特徴的で、レベルの高いボーカリストにとっても決して簡単ではない曲と言えるでしょう。
この曲で重視したいのは【リズム】です。シャッフルのリズム(=タッタ、タッタ、タッタ…という跳ねたリズム)が使われており、曲の最後までこれに従って歌い続けなければなりません。これが崩れてしまい、シャッフル感が失われてしまうと、なんだかスピード感の出ないカッコ悪い印象となってしまいます。
リズム感をより出すには、いくつかのコツがあります。たとえば以下を見てください。
「しんや / とうきょうのーろくじょうはん / ゆめーをみーてた Ah / …」
まず、下線を引いた部分を少し力強く歌ってみましょう。細かくて大変ですが、基本的にはシャッフルの頭(長い方)の音符というだけです。(「ゆめーをみーてた」の部分は、一部例外もあります)このように、しっかりと捉えたいリズムの部分を若干強調することで、よりメリハリのある聴き心地になります。
また、/ で区切った部分では、一瞬「無音(=休符)」を作ることを意識してください。区切りなくだらだら続けてしまうと、横にだらっと広がったメロディラインになってしまいますので、フレーズを粒としてしっかり出せるように練習してみましょう。
さくら(独唱) / 森山直太朗
(動画URL)https://www.youtube.com/watch?v=p_2F2lKV9uA
2003年にリリースされた、今や合唱曲の定番?ともなった森山直太朗さんの楽曲です。「独唱」とあるように、伴奏はピアノのみのため、嫌でもボーカルに注目が行くバラードです。ファルセットを多用した曲のため、より一層細部に気を使って歌い上げなければなりません。
この曲で重視したいのは【発声】です。他の曲でも発声は取り上げられていましたが、この曲はファルセットがたくさん出てくるため発声が崩れやすく、かつ崩れるとそもそもファルセットがうまく出なくなってしまうという悪循環となってしまうため、非常に難易度が高いです。
やはり大切なことは「喉を開けること」です。極端なイメージとしてはオペラ歌手のような声を出すときの喉の開け方ですが、あくまでリラックスした状態で自然にその喉の開き具合を保つことで、声を出すときに余計な抵抗無くまっすぐな発声が可能になります。
ファルセットを使うフレーズの直前は、身構えてしまうことで無意識に喉が締まりがちです。
「どんなに くるしいときも きみはわらっているから」
「さくら さくら いまさきほこる」
のように、ファルセットが始まる前の音符を特に意識してみると良いでしょう。
さいごに
色々な観点から歌を練習できる曲リストをご紹介しました。
もちろんここで紹介しているものの他にも、あなたにとってより勉強になる曲が見つかる可能性もあります。
日頃曲を聞いている中でも、それらがどんなスキルを伸ばす題材となりそうか、考えながら聴いてみるとまた違った発見があるかもしれません。是非あなたに合った練習曲を見つけて、技術を磨いていってみてください。
一人だと曲を見つけられないあなた、選曲に自信がないあなた!ぜひベリーメリーミュージックスクールの体験レッスンに申し込んでみてください。一緒にお手伝いいたします。
この記事を書いた人
1996年 PONY CANYONよりメジャーデビュー。2002年より、ボイストレーナーとしてプロ・アマ、ジャンル、年齢問わず、幅広く指導中。